個人事業主は開業届を提出すべき?書き方や副業の場合も含めて解説
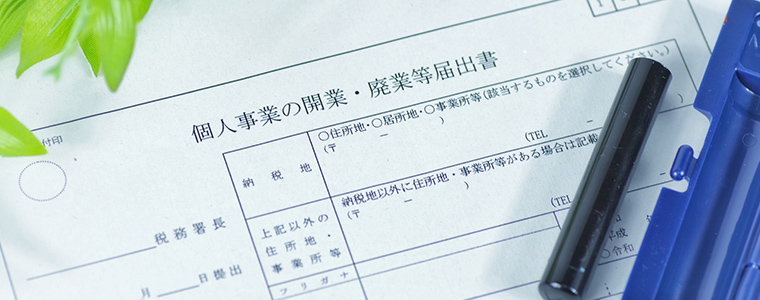
個人で事業を始める場合、「開業届」を税務署に提出する必要があります。しかし、事業収入が少なくても提出するのか、副業で事業を始めた場合も提出が必要なのかと、悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
ここでは、開業届がどのような書類なのか、提出が必要となる場合や提出することのメリットのほか、疑問点なども解説します。
目次
- ・開業届とは?
・個人事業の開業・廃業等届出書
・事業開始等申告書
- ・個人事業の開業届の書き方
- ・開業届の提出は必要?
- ・開業届を提出するメリット
・青色申告による特典が受けられる
・屋号で銀行口座を作れる
・事業を行っている証明になる
・法人用のクレジットカードが持てる
・小規模企業共済に加盟できる
- ・開業届を提出するデメリット
・失業手当が受けられなくなる
・扶養から外れる場合がある
- ・開業届に関する注意点
- ・開業届に関してよくある質問
・Q. 副業でも、開業届は提出すべき?
・Q. 開業届を提出しないデメリットは?
・Q. 開業届の控えはいつもらえる?
・Q. 職業欄の内容はどう書けばいい?
- ・個人事業主におすすめ
ダイナースクラブ ビジネスカード
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード(経費決済専用カード)
・ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴
・ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの特徴
- ・開業届を出すことでさまざまなメリットを得よう
開業届とは?
開業届とは、個人で「事業所得が発生する事業を始めたこと」を税務署に申告するための書類です。個人事業の開業届は2種類あります。
1つ目は税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」、2つ目は都道府県税事務所に提出する「事業開始等申告書」です。なお、個人事業の開業・廃業等届出書も事業開始等申告書も、提出しなくても罰則はありません。それぞれの書類について解説します。
個人事業の開業・廃業等届出書
■個人事業の開業・廃業等届出書の概要
| 内容 | 国税である所得税に関する書類 |
|---|---|
| 提出期限 | 原則、開業日から1ヵ月以内。期限を過ぎても提出は可能 |
| 提出先 | 納税地を管轄する税務署。郵送、e-taxによる提出も可能 |
| 不提出の場合の罰則 | なし。ただし、提出しないと青色申告を利用できない ※青色申告をしたい場合は、一緒に「青色申告承認申請書」を提出する |
| 書式 | 各税務署で入手できるほか、国税庁のWebサイトでもダウンロード可能 個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁) |
| 提出時に必要な書類 | マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類のセット |
事業開始等申告書
事業開始等申告書は地方税である個人事業税に関する書類で、提出しておくと個人事業税の課税対象になった際に通知が届きます。
なお、事業開始等申告書の名称は、都道府県によって異なります。提出期限や書式などを含め、詳しくは居住する地域の都道府県税事務所Webサイトなどで確認しましょう。
提出期限や提出先といった概要は次の通りです。
■事業開始等申告書の概要
| 内容 | 地方税である個人事業税に関する書類 |
|---|---|
| 提出期限 | 各都道府県により異なる |
| 提出先 | 都道府県税事務所 |
| 不提出の場合の罰則 | なし。事業開始等申告書を提出しなくても、確定申告をすれば都道府県にも情報が共有されるので、地方税の納税通知書は届く |
| 書式 | 各都道府県により異なる |
| 提出時に必要な書類 | 居住する地域の都道府県税事務所の情報を確認する |
個人事業の開業届の書き方
ここでは個人事業の開業届の書き方を説明します。個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁)にある項目ごとにみていきましょう。
■個人事業の開業届の記入項目
| 届出先 | 「◯◯税務署長」の「◯◯」には、納税地を所轄する税務署名を記入 |
|---|---|
| 提出年月日 | 開業届の提出日を記入 |
| 納税地 | 住所地・居住地・事業所のうち、該当する項目を選び、住所・電話番号を記入 |
| 上記以外の住所地・事業所等 | 「納税地」に記入した場所以外に、住所地や事業所がある場合は、住所・電話番号を記入(ない場合は空欄) |
| 氏名 | 事業主の氏名を記入 |
| 生年月日 | 事業主の生年月日を記入 |
| 個人番号 | 事業主のマイナンバー(個人番号)を記入 |
| 職業 | 事業主の職業名を具体的に記入 |
| 屋号 | 屋号がある場合は、屋号を記入(ない場合は空欄) |
| 届出の区分 | 「開業」を選択。事業の引き継ぎを受けた場合は、受けた先の住所・氏名も記入 |
| 所得の種類 | 事業内容に該当する所得を選択 |
| 開業・廃業等日 | 開業日を記入 |
| 事務所等を新増設、移転、廃止した場合 | 空欄 |
| 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 | 空欄 |
| 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 「青色申告承認申請書」、消費税に関する「課税事業者選択届出書」の提出の有無を選択 |
| 事業の概要 | 事業内容を具体的に記入 |
| 給与等の支払の状況 | 青色事業専従者や従業員を雇用する場合に記入(雇用しない場合は空欄)。「従業員数」は人数、「給与の定め方」は日給や月給といった給与の支払方法を記入。「税額の有無」は、源泉徴収がある場合は「有」を、ない場合は「無」を選択 |
| その他参考事項 | 特にない場合は空欄 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出の有無を選択 |
| 給与支払を開始する年月日 | 給与の支払開始日を記入(給与支払がない場合は空欄) |
| 関与税理士 | 関与する税理士がいる場合は記入(いない場合は空欄) |
開業届の提出は必要?
開業届は、提出しなくても罰則はありませんので、開業届を出さずに事業を営んでいる個人事業主はいます。
しかし、事業所得が発生する事業を始めたら、開業届の提出が所得税法で義務として定められています。個人で事業を始めた場合や、不動産所得・山林所得が発生する事業を始めた場合にも、本業か副業かに関わらずその活動に事業性があれば、提出が必要です。
ただし、個人で何かしらの収益を得る活動を行っていても、事業性がない場合は提出しなくても問題ありません。たとえば、趣味のハンドメイド作品をフリマアプリなどで販売し、たまに収益があるという場合は、事業性があるとは言い難いため、開業届の提出は不要と判断できます。
事業性があるかどうかは、税務署が明確な基準を定めておらず、活動の目的と継続性、事業規模などから社会通念上「事業」といえるかを、総合的に判断します。一般的には、営利目的で、継続して収入があれば事業とみなされるでしょう。
なお、2022年10月から「所得税基本通達の制定について」の一部改正があり、本業か副業かに関わらず、帳簿書類の保存があれば300万円以下でも事業所得に区分されることになりました。このため、社会通念上、営利目的で継続して収入が発生し帳簿書類を保存している場合は事業とみなされ、開業届の提出が必要になります。ただし、本業の収入の10%未満の場合や毎年赤字である場合など、営利が得られていない状況では帳簿があっても事業とは判断しにくく、雑所得とみなされるため、開業届は不要と判断できます。
開業届を提出するメリット
開業届は、提出義務はあるものの、提出しなかった場合の罰則はありません。
しかし、開業届を提出することで得られるメリットがあります。これらのメリットがあるため、事業所得がある個人事業主は開業届を提出したほうが良いといえます。
青色申告による特典が受けられる
開業届を提出するメリットとして、青色申告による特典が受けられるようになる点が挙げられます。
開業届の提出後、または同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、青色申告による確定申告が可能です。開業届を提出しなければ青色申告はできず、白色申告をすることになります。白色申告は、簡易的な帳簿でよい代わりに、税制優遇などの特典はありません。
青色申告は、基本的に複式簿記方式での帳簿付けが必要になりますが、以下のような特典があります。
<青色申告の主な特典>
- ・最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- ・赤字を最大3年間繰り越せる
- ・事業主と同居する家族従業員への給与を必要経費として計上できる
- ・貸倒引当金を設定できる
青色申告と白色申告のどちらを選ぶかは納税者の自由ですが、通常は青色申告を選んだ方が、特典により納める税金額が小さくなります。
屋号で銀行口座を作れる
開業届を提出することで、屋号付き口座を作りやすくなる点もメリットといえます。金融機関で屋号付き口座を作る際、必要な書類は金融機関ごとに異なりますが、多くは開業届の控えを求められるからです。
屋号付き口座は口座名義が「屋号+名前」となるため、個人名だけの名義よりもきちんと事業を行っていることがわかりやすく、取引先や顧客の信頼を得やすくなります。このほか、屋号が入っていることで振込先が確認しやすくなる点も便利です。
また、屋号付き口座を事業用にすることでプライベート用の口座と明確に分けることができ、お金の管理もしやすくなります。
事業を行っている証明になる
開業届を提出することで、事業を行っている証明になることもメリットです。
オフィスや店舗を借りるとき、融資を受けるときなど、契約に先立つ審査において、自らの職業を証明する必要があるときに、開業届の控えが役立ちます。
法人用のクレジットカードが持てる
開業届を提出すると、法人用のクレジットカードを申し込むことが可能になります。
法人用のクレジットカードとは、事業経費の支払いに用いることを想定した、法人・個人事業主向けのクレジットカードのことです。法人用のクレジットカードを使うことで、経費管理の手間がかからなかったり、ビジネスをサポートする付帯サービスが利用できたりするといったメリットがあります。
小規模企業共済に加盟できる
開業届を提出するメリットとして、小規模企業共済に加盟できることも挙げられます。
個人事業主や小規模企業の経営者向けの退職金制度である「小規模事業共済」に加盟するには、1年目なら開業届の控えの提出が必要です。なお、2年目以降は確定申告書の控えを提出します。
開業届を提出するデメリット
開業届を提出するデメリットとして、事業に大きな影響を与えることはあまりありません。ただし、開業届を提出した場合、「事業を営んでいる」と認識され、失業手当が受けられなくなったり、扶養から外れたりする可能性があります。
該当する場合は開業届を提出したことによるデメリットになり得ますので注意しましょう。それぞれについて解説します。
失業手当が受けられなくなる
会社を退職して失業手当を受けている場合、開業届を提出すると「求職者ではない」と見なされるため、開業手当を提出した時点で失業手当が受けられなくなります。
本業の退職後、失業手当受給期間中に副業の開業届を出す場合などは注意が必要です。
扶養から外れる場合がある
現在、家族の健康保険の扶養枠に入っている人は、開業届を出すことで扶養から外れる場合があります。
扶養枠の範囲は健康保険によって異なり、年収が一定以下であれば個人事業主でも扶養に入れるパターンと、開業届を出した時点で扶養から外れるパターンに分かれます。事前に、現時点で扶養枠に入っている健康保険はどちらのタイプなのか確認しておきましょう。
開業届に関する注意点
開業届では、特に「職業欄」の記入内容に気をつけましょう。職業によって、個人事業税の税率が変わったり、個人事業税が課税されなかったりするためです。
個人事業税の対象となるのは、地方税法で定められた事業(法定業種)です。法定業種に該当するほとんどの職業の税率は5%ですが、畜産業、水産業などは4%、あんま・マッサージ、指圧、はり、きゅうなどは3%となっています。
なお、農業や林業、芸能人、スポーツ選手、作家といった職業は、法定業種に該当しないため、個人事業税はかかりません。
開業届に関してよくある質問
開業届の提出に関して、提出するメリット、デメリットなどはこれまで解説した通りです。そのほか疑問が生じやすいところをまとめて解説します。
Q. 副業でも、開業届は提出すべき?
副業でも、営利目的で継続的に事業を行っているなら、事業性があるといえるので、開業届を提出しておきましょう。帳簿書類を保存している場合、収入の額に関わらず事業所得とみなされます。
なお、開業届を出さなくても、事業での所得が20万円を超えると確定申告が必要です。開業届を出していない場合、この所得は事業所得ではなく雑所得扱いになり青色申告ができませんし、事業所得が赤字になった場合に給与所得と損益通算することもできません。結果として、納税額が大きくなることが多いので、開業届を提出することをおすすめします。
Q. 開業届を提出しないデメリットは?
開業届は、個人事業の開業・廃業等届出書と事業開始等申告書のどちらも、不提出の罰則はありません。
しかし、個人事業の開業・廃業等届出書を提出しないと青色申告が利用できず、最大65万円の青色申告特別控除や最大3年間の赤字の繰り越しといった、青色申告の特典は受けられません。このため開業届を提出した場合に比べて、納税額が大きくなってしまう可能性があります。この点はデメリットといえるでしょう。
開業届は提出期限を過ぎても提出可能ですので、遅れてもできる限り早く出しておくのがおすすめです。
Q. 開業届の控えはいつもらえる?
これまで開業届は、税務署に正本(提出用)といっしょに控えも提出し、税務署は控えに対して、収受日付印の押捺を行っていました。しかし、2025年1月からは、税務署が控えに対する収受日付印の押捺を行わないため、税務署には開業届の正本(提出用)のみを提出するようになっています。
そのため開業届の控えについては、税務署への提出前に、各自がコピーを取るなどして保管しておきましょう。また、収受日付印の押捺がなくなったため、いつ開業届を提出したか、記録しておくことも大切です。
Q. 職業欄の内容はどう書けばいい?
個人事業の開業・廃業等届出書には、職業と事業の概要を記載する欄があります。
書き方はとくに決まっていませんが、参考になるのが、総務省が発表している「日本標準産業分類」です。たとえば、喫茶店の経営者なら、大分類の「M 宿泊業,飲食サービス業」を確認し、職業欄を「喫茶店」、事業の概要には「喫茶店での軽食提供や経営」などと記載します。
また、法定業種も確認しておきましょう。法定業種とは、地方税法に定められている70業種のことです。個人事業主は、事業所得が290万円を超えると個人事業税がかかり、法定業種によって個人税の税率が異なります。さらに、細かい税率は都道府県ごとに違いがあります。個人事業税の課税対象となるかどうか、税率がいくつかにも関わってきますので、きちんと確認しておくことが大切です。
▼個人事業税の経費計上について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください
個人事業税は経費に計上できる?課税されないケースや納付方法も紹介します
個人事業主におすすめ
ダイナースクラブ ビジネスカード
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード(経費決済専用カード)

個人が事業や副業を始めたらまず大切なのは、プライベートのお金と事業の資金を分けて管理することです。
事業経費として計上できるのは、事業を行う上で必要な支出のみですから、過不足なく経費を計上するためにも、プライベートの支出とビジネスのために使ったお金、すなわち経費をしっかりわけておくことが大切になります。この仕訳を簡単にする方法は、ビジネスカードを作り、経費の決済はすべてそのカードで行うようにすることです。
経費はすべてビジネスカードで決済し、ビジネスカードでは経費だけを決済するようにしておけば、プライベートでの支出と混ざってしまうことがありません。また、追加カードの発行が可能、振替口座を法人口座や屋号付き口座に設定できる、ビジネスに役立つ付帯サービスが充実しているなどのメリットも得られます。
ビジネスカードにもさまざまな種類がありますが、ビジネスの場で広く利用することを考えると、信頼につながるカードブランド「ダイナースクラブ」がおすすめです。ダイナースクラブのカードラインナップには、ビジネスに特化した個人カード「ダイナースクラブ ビジネスカード」と、個人向けのダイナースクラブカードに付帯できる経費決済専用の「ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード」があります。
ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴
ダイナースクラブ ビジネスカードは、個人事業主・法人経営者向けのビジネス専用カードです。法人・団体などの代表者や役員、または個人事業主であればお申し込みいただけます。
ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴は次の通りです。

・企業役員や医師、弁護士など、社会的信用の高い人々に利用されてきた実績がある
ダイナースクラブはアメリカで1950年に誕生し、クレジットカード業界をリードしてきたカードです。日本では1961年から発行を開始し、以来、企業の役員、医師や弁護士といった国家資格を有する方など、社会的信用の高い方をメンバーとしてお迎えしてきました。
創業当時から今に至るまでの、クラブの信頼とステータスを高めるための積み上げがあるからこそ、ステータスカードとして広く認知されています。
・ダイナースクラブ ビジネスカードならではのサービスが利用できる
ダイナースクラブカードで利用できるサービスにプラスして、さらにビジネスに役立つ優待特典も多数ご利用いただけます。
たとえば、会計ソフトの優待サービス、税務相談や法律相談などの優待サービスがあるほか、事業承継やM&Aなどのビジネスコンサルティングサービスなどもあります。ゴルファー保険をはじめとするゴルフ優待サービスや加盟店優待、JALオンラインのインターネット予約サービスなどもご利用いただけますので、さまざまなビジネスシーンにご活用ください。
・ポイントの有効期限なしで、ワンランク上の賞品と交換できる
ダイナースクラブのポイントには有効期限がないため、好きなタイミングでポイントをご利用いただけます。貯めたポイントは、厳選グルメや人気メーカーの家電、ゴルフ用品、各種商品券などに交換可能です。いずれもステータスカードにふさわしい、ワンランク上の賞品がラインナップされています。
・利用可能枠に一律の制限なし
ダイナースクラブのカードは、ご利用可能枠に一律の制限はありません。一人ひとりの利用状況や支払い実績に応じて、個別に設定されます。高額なお買い物の際は事前にご相談いただけるサービスもあります。
・登記事項証明書の提出が不要、個人の信用でお申し込みができる
ダイナースクラブ ビジネスカードは、申込時に登記事項証明書(登記簿謄本)の提出は必要なく、事業主の信用情報だけでお申し込みができます。法人経営者・個人事業主のどちらでも、お申し込みが可能です。
・充実のビジネス特典がある
加盟店優待「ビジネス・オファー」、会計ソフト「freee」の優待、会員限定の招待イベントなど、ビジネスカードならではの特典も充実しています。
・従業員を含めた経費の一元管理が可能
ダイナースクラブ ビジネスカードは、18歳以上の従業員に対し、追加カードを4枚まで年会費無料で発行可能です(3、4枚目は1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります)。従業員を含めた経費の一元管理が可能になり、出張費の精算や仮払いの手間も省けます。
■ダイナースクラブ ビジネスカードの主な特徴
| 年会費 | 27,500円(税込) |
|---|---|
| ポイント換算率 | 100円につき1ポイント ※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント |
| 旅行傷害保険 | 最高補償額1億円(海外・国内) |
| 国際ブランド | ダイナースクラブ(Diners Club) |
| 追加会員 | 年会費無料(追加カード発行は4枚まで) ※カード維持手数料:3,4枚目のみ1枚あたり年間5,500円(税込) |
| ETCカード | ・基本会員は5枚まで発行可能 ・追加会員は1会員につき1枚まで発行可能 ※年会費・カード発行手数料無料 |
| ポイント有効期限 | なし |
| ショッピング保険 | 購入日より90日間、年間500万円まで |
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの特徴
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードは、法人カードではありませんが、ダイナースクラブカードや各種提携カードの所有者が、追加で申し込める経費決済専用カードです。法人格を持たない個人事業主でも利用でき、ダイナースクラブカードをプライベート用、ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードを経費用と使い分けることで、経費管理の手間を大幅に軽減できます。

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードには、主に次のような特徴があります。
・プライベート用と経費用に分けて支払口座の設定が可能
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードと、本会員カードとなるダイナースクラブカードとで、別々の支払口座の設定が可能。法人口座の設定もでき、利用代金明細書も別になるため、プライベート用と経費用に分けた経費の管理が容易になります。
・年間手数料は経費に計上可能。ポイントは2枚のカードを合算して使える
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの年間手数料は、事業に関わる支出として経費計上できます。年間手数料が所得税の節税につながるため、お得なクレジットカードといえるでしょう。
なお、クレジットカードの利用で貯まったポイントは本会員カードのポイントと合算して利用できます。
・ダイナースクラブカードならではのサービスを利用できる
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードでも、JALオンラインのインターネット予約サービスなど、ビジネスに役立つサービスをご利用いただけます。さまざまなビジネスシーンにお役立てください。
■ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの主な特徴
| 年間手数料 | 5,500円(税込) |
|---|---|
| ポイント換算率 | 100円につき1ポイント ※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント |
| 国際ブランド | ダイナースクラブ(Diners Club) |
| ETCカード | カード会員本人が所有する車両台数(車載器台数)に応じ5枚まで ※年会費・カード発行手数料無料 |
| ポイント有効期限 | なし |
| 保険 | 本会員カードと同様の保険適用 |
※ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード単体の発行はできません。
開業届を出すことでさまざまなメリットを得よう
開業届は、個人で事業所得が発生する事業を始めたことを、税務署に申告するための書類です。
提出しなくても罰則はありませんが、「提出すると青色申告による特典が受けられる」「屋号付き口座が作れる」「事業を行っている証明になる」「小規模企業共済に加盟できる」といったメリットがあります。営利目的で継続性があれば、社会通念上事業性があるといえるため、副業でも開業届は提出しておきましょう。
開業したら、プライベートな支出と事業での支出を分けて経費管理することが大切ですが、経費決済にビジネスカードを利用すると、経費管理の手間を軽減できます。
ビジネスカードはさまざまな種類があり、どのカードを選ぶか迷うかもしれませんが、ビジネスカードを選ぶ際に重要な要素はステータスです。ステータスの高いクレジットカードを持っているということは、安心できるビジネスを展開している証でもあります。ダイナースクラブは、1950年に米国・ニューヨークのレストランで生まれ、日本で最初のクレジットカードを発行した国際ブランド。安心して使えること、さまざまなサービスが支持されていることなどは、60年以上の歴史が証明しています。
ダイナースクラブ ビジネスカードは、JALオンラインのインターネット予約サービスや会計ソフトとの連携など、ビジネスに役立つ特典が充実。法人でも申し込みに登記事項証明書等が不要で、個人の信用のみで審査を受けられる魅力もあります。 ビジネスに寄り添うダイナースクラブカードをぜひお手元に。
※本記事は、2025年1月現在の情報です。








